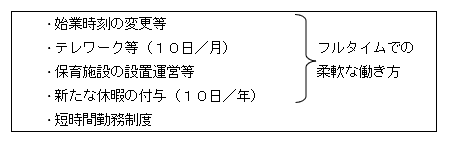法人が支出した取締役の損害賠償金の損金算入の可否が争われた税務判決の紹介 ~横浜地方裁判所令和6年1月17日判決TAINS Z888-2558~
1 はじめに
法人が、その取締役が他の法人の取締役としての職務を怠ったことを理由に負担した会社法429条1項(第三者に対する損害賠償責任)に基づく損害賠償金及び弁護士費用を支払った場合に、当該金員が法人税の所得の計算上、損金の額に算入されるか否かが問題となった税務判決が公表されました。
本判決は、同金員の損金算入を否定し、その結論自体は異論がないものと思われますが、法人が支出した役員等の損害賠償金の税務上の取扱いについて、実務の参考になると思われる判断が示されているので、その内容を紹介します。
2 事案の概要
原告は、土木工事業等を目的とする特例有限会社です。
原告の設立当時の役員は、代表取締役が乙、取締役が乙の二男である甲でした。
原告は、取引先であるA社から、原告の取締役がA社の取締役に就任することについて要請を受け、甲は、A社の取締役に就任しました。
A社は、平成18年頃、株式上場を目指しており、同年から平成21年にかけて、増資を繰り返していました。
その後、甲は、A社の株式の購入者5名から、いわゆる未公開株商法の被害を被ったとして、株式購入代金相当額の損害賠償を求める旨の訴えを提起され、東京地方裁判所は、甲は重大な過失によって取締役としての職務を怠った結果、同訴訟の原告らに損害を生じさせたとして、甲に対し、会社法429条1項の規定に基づく損害賠償等の支払いを命ずる旨の判決を言い渡しました。甲は、同判決を不服として控訴しましたが、控訴審において同訴訟の原告らと和解をして、解決金として1500万円(①)を支払いましたが、その後、原告が同額を甲に対して支払いました。
また、原告は、同訴訟に係る甲の訴訟代理人に対し、弁護士相談料として66万3000円(②)を支払いました。
さらに、甲は、上記訴訟の原告ら以外の者から、未公開株商法による被害を被ったとして、株式購入代金相当額の損害賠償請求を受け、その後、甲は、これらの者の代理人との間で解決金として250万円(③)を支払う旨の合意をし、原告は、同金員を同代理人に支払いました。また、原告は、この件にかかる甲の代理人に対し、弁護士相談料として70万円(④)を支払いました。これらの金員の経理処理としては、原告は、①を雑損失勘定に費用計上するとともに、役員借入金勘定に負債計上し、前述のようにその後、同額を甲に対して支払いました。また、原告は、②から④を支払手数料勘定に計上しました。
原告は、平成26年9月期の法人税について、①、②を損金の額に算入し、平成28年9月期の法人税について、③、④を損金の額に算入して、確定申告をしました(以下、①から④の金員を「本件各金員」といいます。)。
所轄の税務署長は、原告の各事業年度の法人税について、本件各金員を損金の額に算入することはできないことなどを理由に更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしました。
原告が、同更正処分等の取消しを求めて提訴したのが本訴訟です。
3 裁判所の判断
本訴訟の争点は複数あるのですが、以下、「本件各金員は、原告の各事業年度の法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるか否か」という争点について述べます。
(1)法人が役員等の行為による損害賠償金を支出した場合における損金算入の可否
本判決は、法人税法22条3項が、内国法人の損金の額に算入すべき金額について、①収益に係る売上原価等の原価の額、②販管費その他の費用の額及び③損失の額で資本等取引以外の取引に関するものとする旨を規定していることを指摘した上、「所得の金額を計算するに当たり、損金の額に算入することができる支出額は、当該内国法人の業務の遂行上必要と認められるものでなければならないと解され、したがって、その業務との関連性が明らかでない支出額については、これを損金の額に算入することはできないというべきである。」と判示しました。この判断は、異論がないものと思われます。
これに続いて、本判決は、法人税基本通達(以下「法基通」といいます。)9-7-16を引用して次のように判示しました(①、②は筆者による。)。
|
【判示1】 法基通9-7-16は、法人の役員等がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合に、①当該損害賠償金の対象となった行為等が当該法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、当該損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入されるが、②それ以外の場合は、当該役員等に対する債権に当たるとする。 |
このように、本判決は、法基通9-7-16の規定内容が法人税法の解釈として是認されることを示しました。
そして、本判決は、甲の会社法429条1項に基づく損害賠償義務は、甲が(原告ではなく)A社の取締役としての任務を怠ったことにより生じたものであるから、原告の業務の遂行上必要なものとは認められず(※1)、本件各金員は、原告の損金の額に計上することはできない、と判示しました。
(2)本件各金員の役員給与該当性、損金算入の可否
(1)のとおり、本判決は、法基通9-7-16によれば、本件各金員は損金に算入することはできないと述べながら、さらに、本件各金員が原告の役員給与に該当するかという観点からも検討しています。
まず、本判決は、内国法人がその役員に対して支給する給与につき、法人税法34条4項について次のように判示しました。
|
【判示2】 法人税法34条4項は、『債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。』と規定するところ、その『債務の免除による利益その他の経済的な利益』とは、法人が役員のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額のように、法人がこれらの行為をしたことにより、実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいうと解される・・・(中略)・・・ 役員が個人として負担すべき費用を法人が負担することによって当該役員が受ける経済的利益についても、以上の趣旨は該当するものと解されるところ、これを同条1項から3項までの適用上、役員給与に含まれないものとして扱うべき理由はないから、その負担額について、同条4項が定める『その他の経済的な利益』に該当すると解される。 |
この判断も、実は、法人税法34条4項に関する法基通9-2-9(10)の規定内容と同様であり、裁判所が同通達の内容を是認したものです。
このような判断基準を示した上で、本判決は、本件各金員は、いずれも甲が個人的に負担すべき費用を原告が負担することにより、甲に対して経済的な利益を供与したものと認められると認定しました。
少々ややこしいのですが、本判決は、さらに、法基通9-7-17を引用します。すなわち、法基通9-7-17は、同9-7-16(2)に定める債権(その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合(注:判示1の②の場合)のその支出した損害賠償金に相当する金額に係る債権)につき、その役員等の支払能力等からみて求償できない事情にあるため、その全部又は一部を貸倒れとして損金経理した場合(損害賠償金相当額を債権として計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)、当該役員等の支払能力等からみて回収が確実であると認められる部分の金額については、当該役員等に対する給与とすることとしている、とした上で、本件各事業年度における甲の役員報酬の額は、いずれも1800万円であったことからすれば、甲には、原告に対し本件各金員に相当する金額を返済する資力が十分にあり、本件各金員は、甲の支払能力等からみて回収が確実であったと認められる、としました。なお、本件では、法基通9-7-16によれば、原告は、本来、本件各金員を甲に対する債権(求償権)として資産計上すべきでしたが、本判決は、上記括弧書き(損害賠償金相当額を債権として計上しないで損金の額に計上した場合)に該当するので、本件各金員を雑損失や支払手数料の「損金」に計上した原告の「経理処理自体は認められる」と述べています。
以上の事実認定を理由として、本判決は、「本件各金員は、いずれも甲に対する法人税法34条4項所定の『その他の経済的な利益』に該当するから、甲に対する役員給与に該当する。」と判示しました。
本件各金員が法人税法34条4項の「その他の経済的な利益」、すなわち役員給与に該当することになると、次に、損金算入が認められる同条1項各号の「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」に該当するか否かが一応問題になり得ますが、本判決は、本件各金員はこれらのいずれにも該当せず、本件各金員は原告の損金の額に算入することはできない、と結論付けました。
4 検討
法人の役員等がした行為等によって他人に与えた損害につき、法人がその損害賠償金を支出した場合には、本判決もその規定内容を是認した法基通9-7-16が、当該行為が法人の業務に関連するものか否か、故意又は重過失に基づくものであるか否かの2点によりその取扱いを定めています。
すなわち、次のようになります。
①その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。
②その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行には関連しないものである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は、当該役員等に対する債権とする。
この②の場合には、当該賠償金は、第一次的には行為者たる役員等に対してこれを求償すべき性質のものであり、直ちに損金の額に算入することは適当ではないので、まずは役員等に対する求償権(債権)を資産に計上すべきことになります(本判決も同旨)。
さらに、法基通9-7-17によれば、この債権(求償権)については、その役員等の支払能力等からみて求償できない事情にあるため、その全部又は一部に相当する金額を貸倒れとして損金経理した場合には、損金の額に算入されます。ただし、当該貸倒れ等とした金額のうち、その役員等の支払能力等からみて回収が確実だと認められる部分の金額については、これを当該役員等に対する給与とすることになるところ、本判決もこの取扱いを是認しました。(※2)
さらに、本判決では、本件各金員が法人税法34条4項の「債務の免除による利益その他の経済的な利益」に該当するか否かも問題になり、本判決は、「法人が役員のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額」がこれに含まれるとする法基通9-2-9(10)の規定内容を是認しました。この点も本判決の意義であると考えます。
当該金額が法人税法34条4項により役員給与に該当するとされれば、次に同条1項が規定し、損金算入が認められる「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」(それぞれの定義は省略します。)に該当するか否かが問題にはなり得ますが、法人が支出した損害賠償金がこれらのうちのいずれかに該当することはほとんどないと思われます。
本判決は、法人が支出した役員等の損害賠償金の損金算入の可否が争われた珍しい事例であり、その税務上の取扱いについても参考になる事例であると考えたので、紹介した次第です。
以上
※1 原告は、甲に対し、「A社の取締役に就任するが、A社の経営には関与せず、職務を果たす必要がない」というA社からの要請に応ずるという内容の業務命令をしていたのであり、当該業務命令は、経済的には原告とA社との取引関係を強化するもので、原告の利益獲得につながるものであったなどと主張していました。
※2 『DHC コンメンタール法人税法 第2巻』1144頁から1145頁
関連するコラム
-
2025.05.22
橋本 浩史
持分会社の持分払戻請求権の評価額等が問題となった事例 ~名古屋地裁令和6年6月22日判決TAINS Z888-2720~
1 はじめに 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の社員は、死亡によって退社し(会社法607条…
-
2025.04.10
橋本 浩史
有限責任事業組合の組合員に対する課税関係が問題となった事例 ~東京地裁令和6年2月16日判決TAINS Z888-2712(確定)~
1 はじめに 有限責任事業組合(LLP)とは、構成員全員が無限責任を負う民法組合の特例として、「有…
-
2025.03.17
橋本 浩史
M&Aに係るデューデリジェンス費用が有価証券の取得価額に含まれるか否かが争われた事例 ~国税不服審判所令和6年1月24日裁決~
1 はじめに 株式取得などによるM&Aにおいて、買収側が対象企業の価値やリスク等を事前に調査するこ…
-
2025.02.14
橋本 浩史
所得税法72条1項の「損失」の意義が争われた税務判決 ~東京地裁令和6年1月23日判決~
1 はじめに 所得税法72条は雑損控除を定めた規定であり、同条1項は、居住者又はその者と生計を一にす…
橋本 浩史のコラム
-
2025.05.22
橋本 浩史
持分会社の持分払戻請求権の評価額等が問題となった事例 ~名古屋地裁令和6年6月22日判決TAINS Z888-2720~
1 はじめに 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の社員は、死亡によって退社し(会社法607条…
-
2025.04.10
橋本 浩史
有限責任事業組合の組合員に対する課税関係が問題となった事例 ~東京地裁令和6年2月16日判決TAINS Z888-2712(確定)~
1 はじめに 有限責任事業組合(LLP)とは、構成員全員が無限責任を負う民法組合の特例として、「有…
-
2025.03.17
橋本 浩史
M&Aに係るデューデリジェンス費用が有価証券の取得価額に含まれるか否かが争われた事例 ~国税不服審判所令和6年1月24日裁決~
1 はじめに 株式取得などによるM&Aにおいて、買収側が対象企業の価値やリスク等を事前に調査するこ…
-
2025.02.14
橋本 浩史
所得税法72条1項の「損失」の意義が争われた税務判決 ~東京地裁令和6年1月23日判決~
1 はじめに 所得税法72条は雑損控除を定めた規定であり、同条1項は、居住者又はその者と生計を一にす…